交通事故慰謝料の
無料相談はこちら
お気軽にご連絡ください
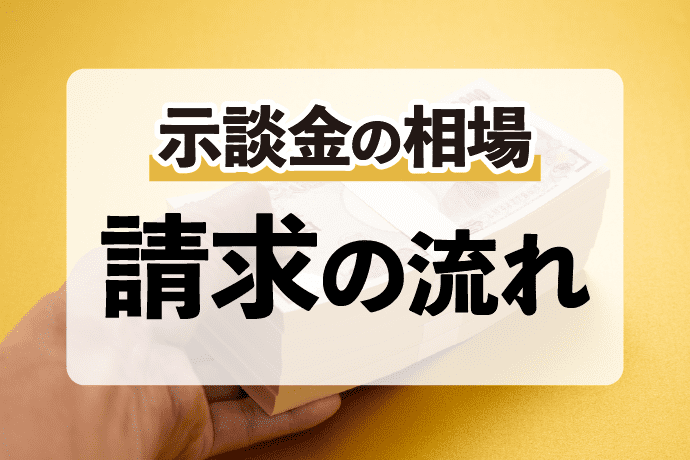
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
この記事でわかること
この記事では、交通事故の示談金に関する基本情報をまとめています。
そもそも示談金とは何なのかという初歩的な疑問を解説し、そこから示談金請求のために交通事故被害者が知っておくべき情報まで掘り下げていくので、初めて交通事故にあって右も左もわからない方は、ぜひ読んでみてください。
目次
示談金とは、「示談交渉によって金額が決められた、交通事故の損害賠償金全体」のことを指します。
交通事故の被害者は、示談交渉を通して加害者に慰謝料や治療費などさまざまな損害賠償金を請求するのですが、これらを全てまとめて「示談金」と呼ぶのです。
示談金に含まれる項目は、交通事故による被害の程度によって異なります。ケガをした場合、後遺障害が残った場合、死亡した場合に分けてみていきましょう。
ケガをした場合
ケガをした場合は、治療期間中に生じた損害額を請求できます。
| 治療関係費 | 治療費、通院交通費、看護費、介護費など |
| 入通院慰謝料 | 入院や通院中に生じた精神的苦痛を補償するお金 |
| 休業損害 | 治療のため仕事を休んだ分の減収に対する補償 |
| 物損の補償 | 壊れた物の修理費、代車費用、評価損など |
後遺障害が残った場合
後遺障害が残った場合の示談金には、「ケガをした場合」の損害賠償金に加えて以下のものが含まれます。
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害により今後も受け続ける精神的苦痛を補償するお金 |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害が残ったために減ってしまった、生涯収入に対する補償 |
後遺障害とは
後遺障害とは、後遺症のうち「後遺障害等級」が認定されたもののことです。
後遺症が残っても、後遺障害等級が認定されなければ後遺障害慰謝料・逸失利益は示談金に含まれません。
後遺障害等級の認定を受ける方法は、『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』をご覧ください。
死亡した場合
| 死亡慰謝料 | 死亡した被害者と、その遺族の精神的苦痛を補償するお金 |
| 死亡逸失利益 | 死亡によって得られなくなった、将来の収入に対する補償 |
| 葬祭費 | 通夜・葬儀や位牌などの費用 |
死亡事故で、亡くなるまでの間に入通院期間があった場合は、「ケガをした場合」の損害賠償金も示談金に含まれます。
示談金の金額は、加害者側の任意保険会社の担当者との示談交渉によって決められます。示談交渉とは、交通事故の加害者と被害者が損害賠償について裁判外の場所で話し合い、和解を試みることです。
そこで次は、示談交渉の流れや注意点について見ていきましょう。
示談交渉は、次の流れで進められます。
示談交渉開始のタイミングは交通事故の種類によって異なり、以下の通りです。
交通事故による損害額は上記のタイミングで確定するので、これより早く示談案が届いても、示談交渉には応じないようにしましょう。
ただし、物損に関する示談金のみ一足先に金額を決めることはあります。
示談交渉そのものについて詳しくはこちらの記事『交通事故の示談交渉で知るべき点』もあわせてご覧ください。
示談交渉で合意に至れなかった場合は、交通事故紛争処理センターをはじめとするADR機関や調停・裁判での解決を試みましょう。
示談交渉では、時効と示談書に注意しましょう。それぞれについて詳しく解説していきます。
交通事故の被害者には、加害者に対して損害賠償請求する権利があります。しかし、損害賠償請求権には「消滅時効」があるので、時効が来る前に示談交渉を終わらせましょう。
損害賠償請求権の消滅時効は、次の期間で成立します。
| ケガのみの場合 | 事故発生日から5年 |
| 後遺障害が残った場合 | 症状固定日*から5年 |
| 死亡事故 | 死亡日から5年 |
*これ以上治療を続けても、大幅な回復は見込めないと診断された日。
交通事故のあと、とくに滞りなく治療や後遺障害等級認定、示談交渉が行われれば、時効までに示談を成立させられます。
しかし、治療や後遺障害等級認定の審査が大幅に長引いたり、示談交渉が行き詰まったりすると、時効に間に合わない可能性があるので注意しましょう。
時効までに示談が成立しそうにない場合は、弁護士に相談することで時効の成立を阻止してもらえます。
示談書に署名・捺印をすると次の効力が生じます。
示談書に記載されている事故概要・被害状況・合意内容・清算条項・作成年月日に間違いがないか、よく確認しましょう。
記載内容に問題があった場合や、その内容で合意して本当に良いのか迷いが生じた場合は、弁護士に相談することがおすすめです。
ただし、事情によっては示談書に署名・捺印した後でも合意内容の撤回や追加の損害賠償請求ができるケースもあります。
示談書についてさらに詳しくはこちらの記事『交通事故の示談書|記載項目やテンプレ』をご覧ください。
示談交渉で加害者側の任意保険会社に弱みを握られてしまうと、交渉の主導権を奪われたり、示談金を減額されたりする可能性があります。
弱みを握られないために、治療中の段階から以下のことに気を付けましょう。
通院頻度があまりにも低かったり、薬をもらうだけ・電気療法を受けるだけなどの漫然治療が続いていたりすると、治療費や慰謝料が支払われない可能性があるので注意しましょう。(関連記事:『交通事故による治療の通院はいつまで?』)
治療が長引くと、加害者側の任意保険会社から症状固定を催促されたり、これ以上の治療費は支払わないと言われたりすることがあります。(関連記事:『交通事故の症状固定はタイミングが重要』)
しかし、これを受けて治療を終わってしまうのは身体にもよくありませんし、慰謝料額にも影響する可能性があります。
弁護士に相談すれば良い対処法をアドバイスしてもらえるので、困った場合は頼ってみましょう。
示談交渉は、被害者自身でも行えますが、以下の点に注意が必要です。
示談交渉が自分でできるかどうかは、こちらの記事『交通事故の示談交渉は自分でもできるのか?注意点をまとめて紹介』でも詳しく解説しています。
交通事故の示談金に関する知識や示談交渉の経験は加害者側の任意保険会社の方が豊富なので、示談交渉は圧倒的に相手方が有利です。
実際に、提示額を増やしてほしいといくら交渉しても十分に聞き入れてもらえず、大幅増額の余地を残したまま低額な示談金で合意せざるを得ない被害者はたくさんいます。
示談交渉の手間やストレスを軽減し、十分な金額を得る最善策は、示談交渉の専門家である弁護士を立てることです。弁護士を立てると費用がかかるというデメリットもありますが、この記事の最後で実質無料で弁護士を立てる方法も紹介しています。
では、本当に弁護士による示談交渉で示談金は増額できるのか、確認していきましょう。実際の事例を紹介していきます。
示談金の増額事例(1)
| ケガ | 左足首骨折による可動域制限(12級7号) |
| 示談金 | 257万円→1185万円 |
後遺障害逸失利益が争点となりましたが、弁護士が裁判提起を視野に入れていることを伝えながら交渉した結果、主張が通りました。
裁判提起をにおわせながら交渉する戦略は、弁護士ならではのものです。加害者側の任意保険会社は裁判になることを嫌がる傾向にあるため、有効な作戦です。
示談金の増額事例(2)
| ケガ | 骨折による手首関節と薬指の可動域制限(11級) |
| 示談金 | 1180万円→1500万円 |
この事例では、加害者側の任意保険会社は一切増額には応じない姿勢をとりました。しかし、弁護士が粘り強く交渉した結果、320万円の増額に成功しました。
時間をかけて粘り強く交渉することも、相手方のかたくなな態度を変化させることも、弁護士だからこそできたことと言えます。
示談金の増額事例(3)
| ケガ | 左上腕骨外科頸骨折による可動域制限(12級7号) |
| 示談金 | 600万円→900万円 |
弁護士が増額を求めたところ、加害者側の任意保険会社は600万円から800万円への増額を認めました。しかし、800万円でもまだ十分ではないと判断した弁護士がさらに交渉を続けたところ、900万円が認められました。
相手方が増額を認めたあと、さらに増額させることは容易ではありません。
弁護士を立てることに迷いがある場合は、こちらの記事も読んでみてください。
『人身事故は弁護士に相談するべき?効果や費用・デメリットを徹底検証』
ここからは、自賠責基準と弁護士基準の示談金相場を実際に比較していきます。
だたし、基本的に実費が支払われる、治療関係費と物損の補償は割愛します。
詳しい計算方法を知りたい場合は、『交通事故|示談金の計算方法を解説!自動計算機で即確認もできる』をご覧ください。
慰謝料には3つの相場金額があるので、金額の算定基準も3つある点がポイントです。慰謝料相場を知るうえで3つの算定基準に関する理解は不可欠なので、先に解説します。
| 自賠責保険基準 | 交通事故の被害者に補償される、最低限の相場金額 |
| 任意保険基準 | 示談交渉で加害者側の任意保険会社が提示する相場金額 |
| 弁護士基準 (裁判基準) | 過去の裁判例をもとにした相場金額 |
任意保険基準の金額は、自賠責保険基準の金額とほぼ同等です。
弁護士基準の金額は任意保険基準の2倍~3倍であり、これは示談交渉がうまくいった場合に被害者が獲得できる、最大金額です。
では、実際に慰謝料の相場金額を見ていきます。任意保険基準の金額は各保険会社で異なり非公開なので、自賠責保険基準の金額を目安にしてください。
※自賠責保険基準は、2020年4月1日以降の事故に適用されるものを紹介します。
弁護士基準の相場は、以下の計算機からも確認可能です。
入通院慰謝料は、自賠責保険会社なら1日当たり4300円とし、「入院日数+通院期間」と「入院日数+実通院日数×2」のどちらか少ない方をかけて算出します。
弁護士基準の場合は、「入通院慰謝料算定表」を用いて算出します。
軽症で3ヵ月間通院し、実通院日数が30日だった場合の入通院慰謝料は、以下の通りです。
入通院慰謝料の相場についてさらに詳しくは、こちらの記事『入通院慰謝料の相場金額は?計算方法と適正額獲得のポイント』でも解説しています。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて決められます。むちうちで認定される12級13号または14級9号の慰謝料額は以下の通りです。
| 等級 | 自賠責保険 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料の相場についてさらに詳しくは、こちらの記事『交通事故の後遺障害慰謝料』でも解説しています。
死亡慰謝料は、自賠責保険基準なら遺族の人数や扶養の有無によって、弁護士基準なら生前の被害者の家庭内における立場によって金額が決まります。
一家の大黒柱で、扶養家族が2人いた場合の死亡慰謝料は以下の通りです。
死亡慰謝料の相場についてさらに詳しくは、こちらの記事『死亡事故の慰謝料相場は?』でも解説しています。
休業損害は「日額×休業日数」で計算されます。日額は以下の通りです。
弁護士基準の方が、より実態に即した休業損害を得られることがわかります。休業損害は、専業主婦や学生でも請求可能です。
休業損害の計算法をもっと詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。
逸失利益の相場金額は、以下のように計算されます。
逸失利益の計算方法は上記の式で統一されていますが、加害者側の任意保険会社は労働能力喪失率や労働能力喪失期間を見積もることで、金額を下げることが多いです。
逸失利益の計算法をもっと詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。
『後遺障害逸失利益|計算方法と適正に獲得するコツをわかりやすく紹介』
交通事故の示談金は、示談交渉で決まった金額がそのまま受け取れるわけではありません。示談交渉で決まった金額から過失割合と同じ割合が減額されるのです。
交通事故が起きた責任が加害者と被害者にどれくらいあるか、割合で示したもの。示談交渉にて、事故当時の状況をもとに決められる。
加害者側の任意保険会社は被害者の過失割合を多めに提示する傾向にあり、鵜呑みにすると必要以上に示談金が減額されます。
適正な過失割合はさまざまな事情を考慮したうえで算出されるので、一度弁護士に妥当な割合を確認することが重要です。
最後に、実質無料で弁護士を立てる方法と、アトム法律事務所の口コミ、無料相談の流れを紹介していきます。
最後まで読めば、法律事務所・弁護士選びでチェックするべき料金・口コミ・実績の網羅が可能です。
アトム法律事務所では、より多くの人の力になれるよう、自己負担金が0円になる料金体制を採用しています。誰でも次のどちらかのプランに該当します。

弁護士費用特約を利用すると、被害者が加入する任意保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。
任意保険に弁護士費用特約がついていれば、利用可能です。(関連記事:『交通事故の弁護士費用相場・弁護士費用特約』)
弁護士費用特約が使えない場合は、相談料・着手金が無料です。相談料・着手金は示談金獲得前に自費で用意する料金で、本来なら合計20万5000円程度かかります。
事案解決後の成功報酬はいただきますが、これは獲得した示談金から支払えるので、自己負担金は実質0円です。
獲得示談金額は、成功報酬を差し引いても十分残ることがほとんどです。
アトム法律事務所では、90%以上のご依頼者様から満足の声をいただいています。ポイントは、納得度の高い実績と丁寧さ・親しみやすさです。
実際にご依頼者様から頂いたお手紙の一部を紹介します。
契約前にも親切にアドバイス頂き、頼むことにしました。先生はとても話やすく、事故に強い先生だったので、思っていたより金額が出てびっくりしました。最初はLINE相談で簡易すぎて半信半疑でしたが、ここでお願いしてとても良かったです。また何かありましたらぜひお願いしたいです。
始めにLINEでの相談に対するお返事がとてもわかりやすくまたやり取りもスムーズだったので安心してお願いしようと思っておりましたが保険会社に提示された金額より大幅に増額していただき感謝しております。
提示された金額が適正なのかどうか分からず話だけでもと思い、法律事務所に相談することにしました。結果、納得できずにいた問題もすっきり解決して頂き示談金は3倍にもなりました。アトム法律事務所はわかりやすく説明をしてくださり、相談料も明確で安心ができました。
その他、ご依頼者様からのお手紙はこちらからご確認ください。
まずは無料の電話・LINE相談です。病院での初回診断が済んだ方ならどの段階でもご相談いただけます。相談の流れを紹介するので、以下に沿ってご連絡ください。
電話相談の流れ

電話相談ではまず、専任のオペレーターが対応します。毎日さまざまな方のお話を聞いているので、うまく相談内容を話せるか不安な場合もご安心ください。
LINE相談の流れ

LINE相談は、自分のペースで相談したい方におすすめです。相談内容のまとめ方に決まりはないので、自由にお送りください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了