交通事故慰謝料の
無料相談はこちら
お気軽にご連絡ください
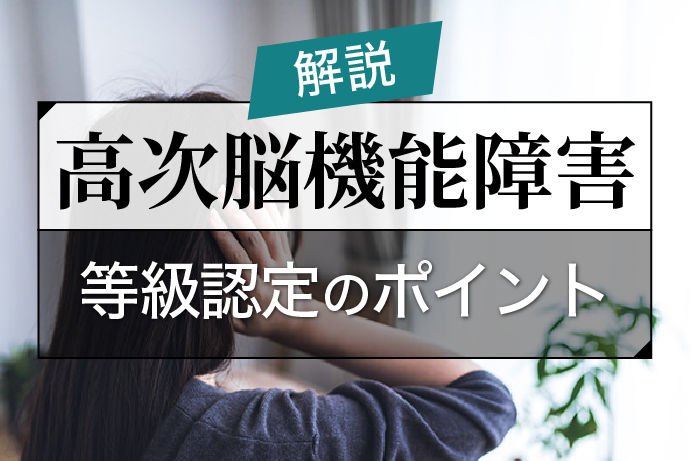
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
高次脳機能障害では、要介護1級・2級、3級・5級・7級・9級に等級認定される可能性があります。しかし、それぞれの認定基準を読んでも用語が難しいうえ抽象的なので、わかりにくいです。
そこでこの記事では、各等級の認定基準をわかりやすく紹介していきます。
等級認定のポイントや後遺障害慰謝料額も紹介しているので、高次脳機能障害の等級認定に関する一通りのことがわかり、今後どう動いていけばいいのかがわかります。
目次
高次脳機能障害の症状は、大きく分けて認知に関する症状・行動に関する症状・人格に関する症状の3種類です。具体的にどのような症状なのか、解説していきます。
高次脳機能障害によって残る後遺症は、以下の通りです。
認知に関する後遺症
行動に関する後遺症
人格に関する後遺症
高次脳機能障害は、脳挫傷やくも膜下出血、くも膜下血腫などの脳損傷や頭部外傷によって生じるものです。この場合、高次脳機能障害のほかにも以下の後遺症を併発する可能性があります。
脳挫傷については『交通事故で脳挫傷に。対応の流れと症状や後遺症・慰謝料をまとめて解説』で詳しく解説しているので、該当する場合は確認してみてください。
上で紹介したような後遺症に対しては、後遺障害等級が認定される可能性があります。しかし、程度によって何級に認定されるかは異なるので、等級認定の基準と、認定されるためのポイントを見ていきましょう。
後遺障害等級認定の流れについてはこちら:『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』
高次脳機能障害が後遺症として残った場合、労災保険が設定した基準を参考にして、要介護1級・2級、3級・5級・7級・9級のいずれかが認定される可能性があります。
それぞれの認定基準と、弁護士を立てた場合と立てなかった場合の各等級の後遺障害慰謝料額を見ていきましょう。
補足
後遺障害慰謝料の相場紹介では、以下の用語を用いるので意味を説明しておきます。
| 弁護士基準 | 弁護士を立てた場合の慰謝料相場 |
| 自賠責基準* | 弁護士を立てなかった場合の慰謝料相場 |
*厳密には、加害者側自賠責保険会社から補償される最低限の慰謝料相場。弁護士を立てなかった場合の慰謝料相場は「任意保険基準」だが、非公開であるためほぼ同等の金額である自賠責基準を紹介。
要介護1級1号は、以下の場合に認定されます。
具体的には…
後遺障害慰謝料
| 弁護士基準 | 2800万円 |
| 自賠責基準 | 1650万円 |
要介護2級1号は、以下の場合に認定されます。
具体的には…
後遺障害慰謝料
| 弁護士基準 | 2370万円 |
| 自賠責基準 | 1203万円 |
高次脳機能障害で3級3号に等級認定されるのは、次のような場合です。
具体的には…
後遺障害慰謝料
| 弁護士基準 | 1990万円 |
| 自賠責基準 | 861万円 |
高次脳機能障害で5級2号に等級認定されるのは、次のような場合です。
具体的には…
後遺障害慰謝料
| 弁護士基準 | 1400万円 |
| 自賠責基準 | 618万円 |
高次脳機能障害で7級4号に等級認定されるのは、以下のような場合です。
具体的には…
後遺障害慰謝料
| 弁護士基準 | 1000万円 |
| 自賠責基準 | 419万円 |
次のような場合、9級10号に等級認定されます。
具体的には…
後遺障害慰謝料
| 弁護士基準 | 690万円 |
| 自賠責基準 | 249万円 |
すでに解説した通り、高次脳機能障害が生じるような怪我をした場合、複数の後遺症が残る可能性があります。
この場合、後遺障害等級認定は各後遺症に対して行われます。遷延性意識障害・てんかんに対する等級認定については『交通事故で脳挫傷に。対応の流れと症状や後遺症・慰謝料をまとめて解説』で解説しているので、確認してみてください。
複数の等級認定を受けた場合は、それらの等級を「併合」した等級に対する後遺障害慰謝料を請求できます。
併合の方法は、以下の通りです。
後遺障害等級1級~14級までの慰謝料額については、『交通事故の後遺障害慰謝料・逸失利益の金額相場|十分な金額を獲得する方法も解説』をご覧ください。
後遺障害等級は、必ずしも認定されるとは限りません。高次脳機能障害の場合は、等級認定を受けるために以下のポイントを押さえる必要があります。
画像所見は、高次脳機能障害が後遺症として残っていることを示す最も客観的かつ医学的な証拠です。MRI画像やCT画像、レントゲン写真を撮って提出しましょう。
ワンポイントアドバイス
異常が画像のどこにあるのか見つけにくい場合は、どこにどんな異常が写っているのか説明するメモを添えることをおすすめします。
画像を見て異常箇所がすぐに見当たらなかった場合、異常なしと見なされる可能性があるからです。
高次脳機能障害によって、実際にどのような変化・不便が生じているのかを伝えることも大切です。この際、「日常生活報告書」や意見書を作成し、家族や職場・学校の人が感じる変化についても記載しましょう。
事故直後に意識障害があったかどうかも重要なポイントです。事故後、6時間以上意識障害があった場合には、高次脳機能障害による後遺症が残りやすいと言われています。該当する場合はその旨を明確に伝えましょう。
等級認定を受けるために
等級認定を受ける際に弁護士の協力を仰げば、上で紹介した「ワンポイントアドバイス」のような、知識と経験に基づく助言を受けられ、妥当な等級認定を受られる可能性が高まります。
たった5%ともいわれる等級認定率をクリアするには、専門家のサポートが必要です。
高次脳機能障害が後遺症として残存した場合、その症状とは一生付き合っていかなければなりません。
だらこそ等級認定や慰謝料請求に対しては不安が尽きないものですが、それらの不安のほとんどは、弁護士に相談する事で解消できます。
なぜ弁護士に相談する事で不安を解消できるのか、よくある3つの不安を例に解説していきます。
高次脳機能障害による後遺症が何級に認定されるかは、後遺障害慰謝料の金額も左右する重要なポイントです。
しかし、ほとんどの被害者にとって後遺障害等級認定は初めてのことですし、きちんと対策ができるのか、適切な等級認定が受けられるのか不安でしょう。
少し調べれば等級認定のポイントやコツ・注意点はわかりますが、それらはあくまで一般論にすぎません。同じ怪我・同じ後遺症でも、程度や状況が人それぞれであるように、本当に必要かつ効果的な対策も人それぞれなのです。
だからこそ、さまざまな等級認定のサポート経験を持つ弁護士のアドバイスを受けることが大切です。
弁護士に相談すれば被害者個人の後遺症・状況にあったアドバイス・サポートをしてもらえるので、ベストな対策をしたうえで等級認定の審査を受けられます。
ポイント
本当に効果的な等級認定の対策は人によって異なる。弁護士に相談すれば、自分の後遺症の症状や程度・状況に応じた対策を考えてもらえる。
損害賠償請求権の消滅時効
後遺障害が残った場合
→症状固定*から5年
*これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めないと医師から判断されること
上記は、交通事故で後遺障害が残った被害者が、加害者に対して損害賠償請求できる時効です。
高次脳機能障害になった被害者は、症状固定の診断を受けたあと、後遺障害等級認定・示談交渉・損害賠償金の受け取りを5年以内に行わなければならないのです。
5年という期間は一見十分にも思えますが、高次脳機能障害では等級認定に数年かかる場合もあります。そのため時効までに示談を成立させられなかったり、時効に迫られて十分に交渉できないまま示談成立を余儀なくされたりすることもあるのです。
これでは、たとえ妥当な等級認定を受けても十分な慰謝料・損害賠償額を得られません。しかし弁護士に相談をしていれば、等級認定の審査に長い時間がかかったとしても時効成立を阻止する手続きを取ってもらえます。
これにより、時効の心配をする必要がなくなるのです。
ポイント
等級認定の審査に数年かかることもある高次脳機能障害では、時効までに示談を成立させられなかったり、時効に間に合わせるため十分な示談交渉ができなかったりする可能性がある。
しかし、弁護士に相談すれば、時効の成立を阻止してもらえ、腰を据えて示談交渉ができる。
十分な慰謝料・損害賠償額を得られなかったがために、被害者や家族の悔しさや怒りが不完全燃焼のまま残ってしまう、今後の生活において「あの時もっと慰謝料を回収できていれば…」という状況が生じてしまう…。
そんなことは何があっても避けたいからこそ不安に感じる慰謝料請求ですが、実際のところ、被害者自身の示談交渉によって十分な慰謝料・損害賠償額を手に入れることは簡単ではありません。
交渉に不慣れな被害者よりも、常日頃示談交渉を行っている加害者側任意保険会社の方が圧倒的に有利だからです。
しかし、専門知識と資格を持つ示談交渉のプロ・弁護士に交渉を任せれば、高額な慰謝料・損額賠償金が得られる可能性はぐんと高まります。
これは、上で紹介した「弁護士を立てた場合と立てなかった場合の慰謝料相場」を比較しても明らかです。
原則としてたった一度しかできない損害賠償請求。万全の態勢を整えて挑みましょう。
ポイント
弁護士を立てずに十分な示談金を得ることは難しい。
被害者の気持ちのためにも、今後の生活のためにも、示談交渉は弁護士を立てて徹底的に行っていきましょう。
高次脳機能障害について等級認定の段階から弁護士に相談した場合、結果通知まで時間がかかりやすい分、他の後遺症に比べて長いお付き合いとなりがちです。
だからこそ、実績はもちろん、ご依頼者様との信頼関係や丁寧で親身なサポートを大切にしているアトムにご相談いただきたいのです。
ここからは、アトムの料金体制・実績と口コミを紹介していきます。事前に弁護士の人柄や雰囲気も確認できる無料相談のご案内もしているので、最後までご確認ください。
アトム法律事務所では、どんな方でも自己負担金0円で相談・依頼ができます。その仕組みは以下の通りです。
| 弁護士費用特約 | 弁護士費用 |
|---|---|
| あり | 弁護士費用を被害者側の任意保険会社に負担してもらえる |
| なし | 相談料・着手金が無料(相場は20万5000円~) 成功報酬は獲得示談金から支払えるので、自己負担金は実質0円 成功報酬は、獲得金額の11%+22万円(税込) |
アトムのポイントは、弁護士費用特約がない方でも費用負担が少なく済むということです。通常なら示談金を獲得する前に20万5000円前後の相談料・着手金をご依頼者様自身で用意していただかなければなりません。
案件が解決しすれば、相談料・着手金をこえる示談金が手に入るとはいえ、急に20万円以上のお金を用意するのは負担が大きいものです。ご依頼から示談金獲得までに時間がかかりがちな高次脳機能障害ならなおさらです。
しかし、そんな方にも安心して頼っていただきたい思いから、アトムでは示談金獲得前にご依頼者様から料金をいただくことはしていません。費用の工面に時間を費やすことなく、すぐにご相談いただけます。
弁護士選びでは実績も非常に大切ですし、これから二人三脚で進んでいくわけですから、口コミ評価も重要です。早速、この2点について紹介していきます。
以下は、高次脳機能障害に関するアトム法律事務所の実績です。いずれも、等級認定の段階から幣事務所の弁護士がサポートをしました。
実績(1)
| 怪我 | 大腿骨骨折、右膝骨折、右手骨折、左足首骨折、高次脳機能障害 |
| 等級 | 併合6級 |
| 獲得金額 | 4344万円 |
実績(2)
| 怪我 | 高次脳機能障害 |
| 等級 | 7級4号 |
| 獲得金額 | 4183万円 |
事例(3)
| 怪我 | くも膜下出血、高次脳機能障害、頚椎損傷、頚椎骨折、手の痺れ、右腕開放骨折、右腕粉砕骨折 |
| 等級 | 併合9級 |
| 獲得金額 | 3492万円 |
アトム法律事務所の高次脳機能障害に関する解決実績は、『頭部の解決実績一覧』からご確認いただけます。
つづいて、アトム法律事務所のご依頼者様から頂いたお手紙を一部紹介していきます。

(略)無料のLINE相談でも親切に対応していただき感謝しています。
交通事故の保険のことなど無知な私には強い味方になってもらい、1ヶ月半ほどで慰謝料も2倍になり、本当にお願いしてよかったと思っています。
アトム法律事務所・ご依頼者様からの声
(略)提示された賠償金の額が本当に妥当かどうか、いくつかの法律事務所に相談したところ、電話受付の方の親切、丁寧で押し付けてくることがなかった事がきっかけとなりアトム法律事務所にお世話になることを決めました。(略)そして今、納得のいく額が受け取ることができました。
アトム法律事務所・ご依頼者様からの声
(略)始めにLINEでの相談に対するお返事がとてもわかりやすくまたやり取りもスムーズだったので安心してお願いしようと思っておりましたが保険会社に提示された金額より大幅に増額していただき感謝しております。(略)
アトム法律事務所・ご依頼者様からの声
最後に、無料電話・LINE相談の流れを紹介します。どちらかお好きな方を選んでください。
電話相談は、声を通じて弁護士の人柄や雰囲気まで確認しやすい点が特徴です。
LINE相談は、まとまった時間が取れない方、じっくり相談内容をまとめたい方におすすめです。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了